
【警告】現金で相続するのは大損です!富裕層の9割が実践する不動産を使った相続対策の裏側
「親が残してくれた大切な財産…でも、もし相続したら一体いくらの税金がかかるんだろう?」「うちには関係ないと思っていたけど、実家の土地と少しの預貯金だけでも、相続税の対象になるかもしれない…」
あなたも今、漠然と、しかし確実に近づいてくる「相続」という現実に、こんな不安を抱えていませんか?大切な家族の資産が、対策をしなかったばかりに税金でごっそり持っていかれるとしたら、それはあまりにも悲しいことです。
この不安を放置してはいけません。国税庁の統計によれば、相続税の課税対象者は年々増加しています。何もしなければ、数百万円、場合によっては数千万円という想像以上の税金が、ある日突然あなたの家族に重くのしかかります。さらに恐ろしいのは、財産分割をめぐって兄弟姉妹が対立する「争族(そうぞく)」です。現金と違って分けにくい不動産が原因で、昨日まで仲の良かった家族がバラバラになってしまうケースは、決して他人事ではないのです。
実は、多くの資産家や計画的なご家庭では、この最悪の事態を回避するための「ある方法」を賢く実践しています。それは「投資用不動産を活用した相続対策」です。なぜなら、同じ1億円の資産でも、現金で持っているのと不動産で持っているのとでは、国が定める評価額が全く異なり、結果として相続税を劇的に圧縮できるからです。これは裏技でも脱税でもなく、法律で認められた正当な権利であり、知っているか知らないかで未来が大きく変わる「知識」なのです。
実際にこの方法を実践した方からは、「おかげで相続税の負担を80%も削減でき、納税資金に困らずに済みました」「分割しやすい区分マンションを選んだことで、子供たちに公平に資産を残せ、揉め事を未然に防げました」といった喜びの声が数多く寄せられています。
この記事では、なぜ投資用不動産がこれほどまでに有効なのかという基本的な仕組みから、具体的な節税シミュレーション、始める前に必ず知っておくべきリスクと回避策、そしてプロが実践する「失敗しない物件選びの鉄則」まで、あなたが知りたい情報のすべてを網羅しました。
未来の家族の笑顔と、大切な資産を守るための準備は、今日から始められます。さあ、まずはこの記事を最後まで読んで、後悔しない相続対策への第一歩を踏み出しましょう。
なぜ投資用不動産が相続対策の王道なのか?節税の仕組みを徹底解説
【基本のキ】現金1億円と不動産1億円の評価額は全く違う!
相続対策で投資用不動産が最も有効な手段の一つとされる最大の理由は、現金を不動産に換えるだけで、相続税を計算する際の元となる「財産の評価額」を大幅に引き下げることができるからです。これは、相続税法で定められた財産の評価方法の違いによるもので、合法的に認められた極めて効果的な節税手法と言えます。
なぜ、このような評価額の差が生まれるのでしょうか。その理由は、財産の種類によって評価ルールが全く異なるからです。例えば、現金や預貯金は非常にシンプルで、1億円の現金はそのまま「1億円の価値がある」と100%の額面通りで評価されます。一方で、不動産の相続税評価額は、実際に市場で取引される価格(時価)ではなく、国が定めた公的な価格である「路線価(土地)」と「固定資産税評価額(建物)」を基準に計算されます。この公的な価格は、一般的に時価よりも低く設定されており、土地(路線価)は時価の約80%、建物(固定資産税評価額)は時価の約50%~70%が目安とされています。この時点で、現金を不動産に変えるだけで、資産の評価額が2割から5割程度圧縮される可能性があるのです。
具体例を考えてみましょう。ここに現金1億円を持っているAさんと、その1億円で都内の投資用マンション(土地4,000万円、建物6,000万円)を購入したBさんがいるとします。Aさんの相続財産は当然1億円です。一方、Bさんのマンションの相続税評価額はどうなるでしょうか。仮に路線価が時価の80%、固定資産税評価額が時価の70%だとすると、土地は4,000万円×80%=3,200万円、建物は6,000万円×70%=4,200万円となり、合計の評価額は7,400万円となります。つまり、Bさんはマンションを購入しただけで、何もしなくても財産評価額を2,600万円も圧縮できたことになるのです。相続税率が30%だった場合、これだけで780万円もの節税に繋がります。
このように、現金のまま保有するのに比べて、不動産として保有する方が相続税評価額を大きく引き下げることが可能です。これが、多くの資産家が相続対策として投資用不動産を活用する根本的な理由なのです。
図解で納得!相続税評価額が劇的に下がる2つのカラクリ
投資用不動産が相続税評価額をさらに大きく引き下げるのには、「時価と公的評価額の差」に加えて、「賃貸に出すことによる評価減」という、もう一段階強力なカラクリが存在します。この仕組みを理解することが、節税効果を最大化する鍵となります。
そのカラクリとは、「貸家建付地(かしやたてつけち)」と「貸家(かしや)」の評価減です。自分が住むのではなく、第三者に建物を「賃貸」している場合、その土地や建物は所有者の自由な使用が制限されていると見なされます。そのため、相続税を計算する上で、その制限分だけ評価額を下げてもらえるのです。具体的には、土地(貸家建付地)は「自用地評価額 × (1 – 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)」という計算式で評価額が下がります。また、建物(貸家)も「固定資産税評価額 × (1 – 借家権割合 × 賃貸割合)」で評価が下がります。借家権割合は全国一律30%と定められており、満室経営(賃貸割合100%)であれば、建物の評価額は単純に30%オフになる計算です。
先ほどのBさんの例で、この効果を見てみましょう。Bさんのマンションの評価額は7,400万円(土地3,200万円、建物4,200万円)でした。このマンションを満室で賃貸に出していたとします。借地権割合を70%と仮定すると、土地の評価額は「3,200万円 × (1 – 70% × 30% × 100%)」= 2,528万円まで下がります。建物の評価額は「4,200万円 × (1 – 30% × 100%)」= 2,940万円まで下がります。結果、合計の評価額はなんと5,468万円にまで圧縮されました。現金1億円と比較すると、評価額は約45%も圧縮され、半分近くになった計算です。相続税率30%なら、節税額は(1億円 – 5,468万円)× 30% = 約1,360万円にも達します。これはまさに、知っているか知らないかで大きな差がつく「制度の活用」と言えるでしょう。
このように、投資用不動産は「①時価と評価額の差」と「②賃貸による評価減」という二段構えの仕組みによって、相続財産を劇的に圧縮することが可能です。これが、単なる不動産ではなく、「投資用」不動産が相続対策に強いと言われる所以なのです。
始める前に知るべき!投資用不動産相続の光と影
メリットだけじゃない!専門家が警鐘を鳴らす5つの重大リスク
投資用不動産による相続対策は、その大きな節税効果から非常に魅力的に見えますが、安易に飛びつく前に、不動産投資そのものに内在する5つの重大なリスクを正確に理解し、対策を講じることが不可欠です。これらのリスクを軽視すれば、節税額以上の損失を被り、結果的に大切な資産を減らしてしまう本末転倒な事態に陥りかねません。
なぜリスクの理解が重要かというと、相続対策という目的が先行するあまり、投資対象である不動産の収益性や資産性といった本質的な価値を見誤るケースが後を絶たないからです。「節税になるなら何でもいい」という考えは非常に危険です。不動産は購入して終わりではなく、長期にわたって保有・経営していく資産です。その過程で予期せぬ事態が発生すれば、家賃収入が途絶えたり、多額の支出が発生したりして、計画が大きく狂ってしまいます。相続する子供たちに、収益を生まない「負の財産」、すなわち「負動産」を押し付ける結果になっては元も子もありません。だからこそ、光の部分だけでなく、影の部分にもしっかりと目を向ける必要があるのです。
具体的に、特に注意すべき5つのリスクと対策を見ていきましょう。
-
空室・家賃下落リスク:最も基本的かつ最大のリスクです。入居者がいなければ家賃は1円も入ってきません。節税効果の根幹である「賃貸」が前提であるため、空室は致命的です。対策としては、単身者需要が安定している都心や主要駅の徒歩圏内など、賃貸需要が長期的に見込めるエリアの物件を選ぶことが鉄則です。
-
老朽化・修繕リスク:建物は時間とともに劣化します。給湯器の故障、エアコンの交換、外壁塗装など、突発的または計画的な修繕費用が発生します。これらの費用を想定せずに利回り計算をしていると、実際の収支は大きく悪化します。対策は、長期修繕計画がしっかりしている物件を選び、毎月のキャッシュフローから修繕積立金を確保しておくことです。
-
災害リスク:地震、水害、火災など、日本は自然災害の多い国です。災害で建物が損壊すれば、資産価値が失われるだけでなく、修復に多額の費用がかかります。対策として、ハザードマップを確認して災害リスクの低い立地を選ぶこと、そして適切な火災保険や地震保険に加入することは必須です。
-
流動性リスク:不動産は現金や株と違い、売りたいと思った時にすぐに現金化できるとは限りません。急にまとまった資金が必要になった場合や、相続した子供が売却を望んだ場合に、買い手がつかず「塩漬け」状態になるリスクがあります。対策は、やはり換金性の高い、多くの人が欲しがる都心部の需要が安定した物件を選ぶことです。
-
金利上昇リスク:ローンを組んで物件を購入した場合、将来的に金利が上昇すると返済額が増加し、収支を圧迫します。対策としては、金利が上昇しても耐えられるよう、自己資金を多めに入れる、繰り上げ返済を計画するなど、余裕を持った資金計画を立てることが重要です。
このように、投資用不動産には節税メリットの裏側に無視できないリスクが存在します。しかし、これらのリスクは事前に認識し、適切な物件選びと計画を立てることで十分にコントロール可能です。メリットとデメリットを天秤にかけ、冷静に判断することが成功への第一歩です。
相続対策の成功は物件選びで9割決まる!「負動産」にしないための鉄則
結論から言えば、投資用不動産を活用した相続対策が成功するか失敗するかの9割は、最初の「物件選び」で決まります。節税効果(相続税評価額の圧縮率)と、投資対象としての収益性・資産性の両方を高いレベルで満たす物件を見極めることが、将来にわたって価値のある資産を家族に残すための絶対条件です。
なぜなら、前述のリスクを回避し、相続対策の目的を達成するためには、物件そのものが持つポテンシャルがすべてだからです。例えば、いくら評価額の圧縮率が高くても、入居者がつかず毎月赤字を垂れ流すような物件では、相続税を節税できたとしても、それ以上のキャッシュを失うことになります。また、相続した子供たちが売却したくても全く売れないような資産価値の低い物件では、結局のところ誰も幸せになりません。相続対策のゴールは、単に目先の税金を減らすことではなく、「優良な資産を円満に次世代へ引き継ぐこと」です。そのためには、長期的に安定した家賃収入を生み出し、かつ市場価値が落ちにくい、いわば「守り」と「攻め」のバランスが取れた物件を選ぶ必要があるのです。
では、具体的にどのような物件を選べば「負動産」化を避けられるのでしょうか。プロが実践する物件選びの鉄則は、主に以下の3つのポイントに集約されます。
-
立地:何よりも「賃貸需要の強さ」を最優先する
言うまでもなく、立地は最も重要な要素です。見るべきは、現在の利回りだけでなく、「10年後、20年後も入居者に困らないか」という視点です。具体的には、人口が増加傾向にある都市部、特に東京23区などの単身者向け賃貸需要が底堅いエリアが有力候補となります。最寄り駅から徒歩10分以内、できれば複数路線が利用できるターミナル駅へのアクセスが良い場所は、景気変動の影響を受けにくく、資産価値も維持されやすい傾向にあります。 -
物件種別:管理がしやすく分割もしやすい「区分マンション」
相続対策の初心者には、一棟アパートやマンションよりも、管理の手間が少なく、流動性も高い「区分所有のワンルームマンション」が推奨されることが多いです。管理は管理会社に任せることができ、将来的に相続人が複数いる場合でも、「長男にはA物件、次男にはB物件」というように現物で公平に分割(現物分割)しやすいのが大きなメリットです。「争族」のリスクを低減させる効果も期待できます。 -
建物:資産価値を維持する「管理状態」と「構造」を見極める
新築や築浅物件は魅力的ですが、価格が高く、家賃の下落率も大きい傾向があります。一方で、適切な修繕がなされてきた中古物件は、価格が手頃で利回りも安定している場合があります。重要なのは、建物の構造(耐久性の高いRC造やSRC造か)と、管理組合が機能し、長期修繕計画がきちんと立てられ実行されているかです。物件の見た目だけでなく、管理状態を示す書類を必ず確認しましょう。
したがって、相続対策の成功は、目先の節税額や利回りの数字だけに惑わされず、長期的な視点で「賃貸需要」「換金性」「管理状態」という3つの軸から、資産価値の落ちにくい優良物件を厳選できるかにかかっています。これこそが「負動産」を掴まないための絶対的な鉄則です。
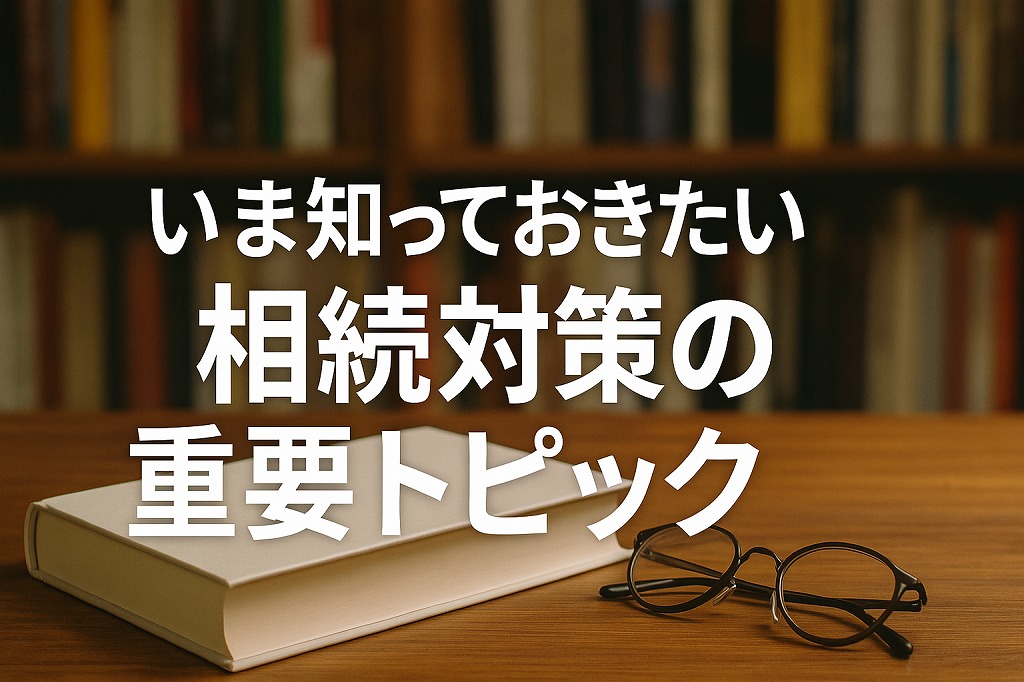
いま知っておきたい相続対策の重要トピック
タワマン節税はもう古い?評価額改正の影響と今取るべき新戦略
かつて相続対策の切り札として絶大な人気を誇ったタワーマンション(タワマン)ですが、2024年1月1日以降に相続が発生した物件から適用される税制改正により、以前のような劇的な節税効果は期待しにくくなりました。このルール変更を正確に理解し、今後の戦略を再考することが極めて重要です。
なぜ、このような改正が行われたのでしょうか。その背景には、タワマンの「時価(実際の売買価格)」と「相続税評価額」の間に著しい乖離があり、それを利用した行き過ぎた節税が問題視されたことがあります。特に、高層階ほど眺望などの付加価値から時価は高くなるにもかかわらず、相続税評価額の計算基準となる固定資産税評価額は床面積が同じなら低層階も高層階も同じでした。この「歪み」を是正し、課税の公平性を確保する目的で、国は評価額の計算ルールを見直したのです。具体的には、時価と評価額の乖離率(評価水準)が0.6未満の場合、評価額を時価の60%まで引き上げるという補正措置が導入されました。
この改正が与える影響は非常に大きいです。例えば、時価1億円のタワマン高層階の部屋があり、これまでのルールでは相続税評価額が2,000万円だったとします。この場合の乖離率は0.2(2,000万円 ÷ 1億円)となり、新たな基準である0.6を大きく下回ります。そのため、改正後は最低でも時価の60%、つまり6,000万円(1億円 × 60%)まで評価額が強制的に引き上げられることになります。この例では、評価額が3倍になり、結果として相続税額も大幅に増加する可能性があるのです。
では、タワマンはもはや相続対策として無価値なのでしょうか?答えは「NO」です。確かに以前ほどの爆発的な節税効果は薄れましたが、依然として現金で持つよりは評価額を圧縮できるケースが多いのは事実です。重要なのは、今後の新戦略として、「節税効果だけを過度に期待しない」ことです。タワマンを選ぶ際は、節税効果と同時に、都心一等地ならではの資産価値の維持しやすさ、賃貸需要の高さ、ブランド価値といった「不動産投資」としての魅力をより重視する視点が必要になります。節税はあくまで副次的な効果と捉え、長期的に価値が落ちない優良資産を選ぶという王道に立ち返ることが、新しいタワマン節税戦略と言えるでしょう。
結論として、タワマン節税は「終わった」わけではありませんが、その効果は大きく変化しました。これからは最新のルールを前提に、過度な期待をせず、不動産としての本質的な価値を見極めた上で、慎重に検討するべき相続対策の一つと位置づける必要があります。
不動産だけじゃない!他の相続対策(生前贈与・生命保険)との徹底比較
投資用不動産は非常に有効な相続対策ですが、それが全てのご家庭にとって唯一無二の最適解とは限りません。資産状況や家族構成によっては、「生前贈与」や「生命保険の活用」といった他の対策と組み合わせる、あるいはそちらを優先する方が良いケースも存在します。それぞれのメリット・デメリットを理解し、複眼的な視点で対策を検討することが重要です。
なぜなら、各相続対策には得意・不得意があり、効果を発揮する場面が異なるからです。投資用不動産は、大きな資産を一度に圧縮できるダイナミックな効果が魅力ですが、購入資金が必要であり、流動性リスクや運営の手間といったデメリットも抱えています。一方で、生前贈与は少額からでも始められ、確実に資産を次世代に移転できますが、年間110万円の基礎控除を超える贈与には贈与税がかかり、また相続開始前7年以内の贈与は相続財産に持ち戻されるなど、ルールが複雑化しています。生命保険は、受取人が指定した現金を確実に残せること、そして「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠があるのが大きな強みですが、当然ながら保険料の支払いが必要です。このように、一つの対策に固執するのではなく、それぞれの特性をパズルのように組み合わせることで、より強固で柔軟な対策を構築できるのです。
具体的に、どのような場合にどの対策が有効か比較してみましょう。
-
投資用不動産が向いているケース:
-
数千万円以上のまとまった現預金を保有している。
-
相続税評価額を大きく圧縮したい。
-
インフレ対策として、現物資産を保有したい。
-
家賃収入というインカムゲインも得たい。
-
-
生前贈与が向いているケース:
-
時間をかけてコツコツと資産を移転させたい。
-
子供や孫の住宅購入資金や教育資金を援助したい(特例制度あり)。
-
相続人以外(孫など)にも財産を渡したい。
-
不動産のように運営の手間がかかるものは避けたい。
-
-
生命保険の活用が向いているケース:
-
相続財産が不動産ばかりで、納税資金となる現金が少ない。
-
特定の相続人に、他の相続人の干渉を受けずに現金を残したい(遺産分割の対象外)。
-
「争族」を避けるため、遺産分割とは別の資金枠を用意したい。
-
非課税枠を最大限活用して、手堅く節税したい。
-
例えば、「主な資産は自宅と預貯金1億円。相続人は子供2人」というご家庭の場合、1億円全額を不動産に換えるのではなく、「5,000万円で都心の区分マンションを購入し、3,000万円は生命保険に加入して納税資金と争族対策に備え、残りの2,000万円は暦年贈与で孫の教育資金として少しずつ渡していく」といった複合的なプランが考えられます。
このように、投資用不動産、生前贈与、生命保険にはそれぞれ一長短があります。あなたの家族構成、資産の内訳、そして何よりも「誰に、何を、どのように残したいか」という想いに合わせて、これらの選択肢を最適に組み合わせることが、後悔しない相続対策の鍵となるのです。
失敗しないための具体的な進め方と7つのステップ
投資用不動産による相続対策を成功に導くためには、思いつきで行動するのではなく、明確に定められた7つのステップに沿って、計画的かつ慎重に進めていくことが絶対不可欠です。このロードマップを無視して進むと、思わぬ落とし穴にはまり、時間もお金も無駄にしてしまう可能性があります。
なぜなら、相続対策は税務、法務、不動産投資という複数の専門領域が絡み合う複雑なプロジェクトだからです。まず、自分たちの資産が現状でどれくらいの価値があり、どれほどの相続税が見込まれるのかというスタート地点を把握しなければ、対策の規模や方向性すら決められません。また、節税ばかりに目が行き、誰にどの財産を渡すかという遺産分割の視点が欠けていると、深刻な家族間のトラブル「争族」を引き起こしかねません。さらに、不動産購入の資金計画、対策を始めるべき適切なタイミング、税務署から「やりすぎ」と見なされないための注意点など、各段階で専門的な判断が求められます。これらを一人で完璧に進めるのは至難の業であり、信頼できる専門家との連携が成功の鍵を握ります。そして最後に、購入から管理、相続発生後までの一連の流れを俯瞰して理解しておくことで、安心してプロジェクトを完遂できるのです。
それでは、具体的に7つのステップを駆け足で見ていきましょう。
-
STEP1:現状把握と相続税試算:まずは、預貯金、有価証券、不動産、生命保険など、全ての財産をリストアップし、財産目録を作成します。その上で、国税庁のウェブサイトなどを使い、おおよその相続税額をシミュレーションします。この数字が、対策の必要性と目標設定の基準となります。
-
STEP2:遺産分割の方針決定:誰にどの財産を相続させたいか、家族で話し合います。不動産は分けにくいため、相続人が複数いる場合は、売却して現金で分けるのか、共有名義にするのか、あるいは分割しやすい区分マンションを複数購入するのかなど、揉めないための着地点をあらかじめ考えておくことが重要です。遺言書の作成も有効な手段です。
-
STEP3:資金計画とローン活用:自己資金はいくら投入できるのか、ローンは組むのかを検討します。ローンを組むと、その借入金は相続財産から差し引かれる「債務控除」が適用され、さらなる節税効果が期待できます。ただし、返済計画には十分な注意が必要です。
-
STEP4:開始時期の決定:相続対策は、気力・体力・判断力が充実しているうちに、なるべく早く始めるのが鉄則です。特に、相続発生の直前に慌てて不動産を購入すると、税務署から租税回避行為とみなされ、否認されるリスクが高まります。最低でも3年以上、できれば5年以上の余裕を持って計画的に進めましょう。
-
STEP5:税務リスクの確認:前述のタワマン節税の改正のように、行き過ぎた節税には規制が入ります。時価と評価額の乖離が極端に大きい物件や、購入後すぐに売却するような不自然な取引は否認リスクを伴います。税理士に相談し、社会通念上、常識の範囲内での対策を心掛けましょう。
-
STEP6:パートナー選び:相続対策の実績が豊富な不動産会社と税理士を見つけることが最も重要です。不動産会社は物件を紹介するだけでなく、購入後の賃貸管理まで安心して任せられるかを見極めます。税理士には、全体のスキーム作りから税務申告までをサポートしてもらいます。
-
STEP7:実行と管理:プランが決まったら、物件の購入、賃貸募集、管理会社との契約などを進めます。購入後も、安定した賃貸経営を維持し、定期的に資産状況や税制の変更をチェックしていくことが大切です。
このように、一つ一つのステップを着実に、そして専門家の助けを借りながらクリアしていくことこそが、失敗しない投資用不動産相続の唯一の道です。焦らず、計画的に、大切な家族のための資産承継を成功させましょう。
まとめ:未来の家族のために。今日から始める後悔しない相続対策
この記事では、投資用不動産を活用した相続対策について、その強力な節税効果の仕組みから、避けては通れないリスク、最新の税制改正、そして成功に導くための具体的な7つのステップまで、網羅的に解説してきました。
重要なポイントを改めて整理します。
-
投資用不動産は、現金を不動産に換えることで「評価額」を大きく圧縮し、相続税を効果的に節税できる。
-
節税効果だけでなく、「空室」「老朽化」などの不動産投資リスクを直視し、長期的に価値が落ちない優良物件を選ぶことが成功の9割を決める。
-
タワマン節税のルール変更など、税制は常に変化する。最新情報を把握し、不動産以外の選択肢(生前贈与・生命保険)とも比較検討することが重要。
-
相続対策は計画性が命。現状把握から専門家選びまで、明確なステップに沿って慎重に進める必要がある。
相続対策は、「いつかやろう」と思っているうちに、あっという間に時間が過ぎてしまうものです。そして、いざという時に「もっと早くやっておけばよかった」と後悔しても、時間は戻ってきません。
これは単なる節税の話ではなく、あなたが築き上げてきた大切な資産と、愛する家族の未来を守るための、極めて重要な準備です。
しかし、決して一人で全ての悩みを抱え込む必要はありません。
この記事を読んで少しでも「うちも考えなくては」と感じたなら、まずは相続に詳しい税理士や不動産の専門家に、現状を相談してみることから始めてみてはいかがでしょうか。
あなたの今日の一歩が、未来の家族の安心と笑顔に繋がる、最も価値ある投資となるはずです。


